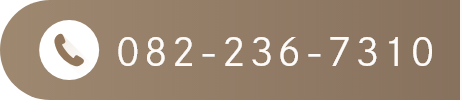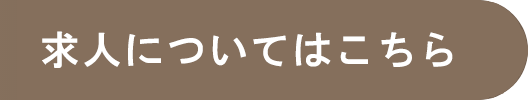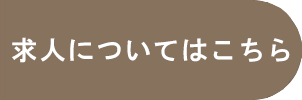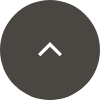医科・歯科間の情報提供・共有する際の算定について
こんにちは、算定チームです!
今回は、医科・歯科間の情報提供・共有する際の算定についてお話させていただきます。
保険医療機関が診療に基づいて、他の保険医療機関での診療の必要があると認め、
患者さまの同意を得て、診療状況を示す文書(情報提供書/いわゆる”紹介状”のことです!)を添えて紹介を行った場合、診療情報提供料(Ⅰ)が算定できます。
これは患者さまについて医療機関・多職種間内で円滑な連携を取るために欠かせない書類であり、算定となっています。
「診療情報提供料(Ⅰ)」について詳しくは過去に掲載しているのでそちらをご覧いただければと思います。
→https://hinode-clinic.com/blog/186697
では歯科に対して情報提供をする際の算定ですが、当院のように歯科のない医療機関が、歯科へ情報提供をした場合上記の「診療情報提供料(Ⅰ)250点」を算定することができます。
またその際、同提供料の加算があります。
・歯科医療機関連携加算1(100点)
<算定要件>
医療機関(歯科診療を行うものを除く)が、歯科を標榜する医療機関に対して、口腔内の管理が必要と判断した患者の情報提供を、
以下のアまたはイで行った場合に算定。
ア)がん治療や手術などを行う患者について、手術前に歯科医師による周術期口腔機能管理の必要性を認め、歯科を標榜する保険医療機関に対して情報提供を行った場合。
イ)医科保険医療機関または医科歯科併設の医療機関の医師が、歯科訪問診療の必要性を認めた患者に、在宅歯科医療を行う、歯科を標榜する保険医療機関に対して、
診療情報を示す文書を添えて当該患者の紹介を行った場合。
・歯科医療機関連携加算2(100点)
<算定要件>
保険医療機関が、周術期等における口腔機能管理の必要を認め、患者又はその家族等の同意を得て、
歯科を標榜する他の保険医療機関に当該患者が受診する日(手術前に必要な歯科診療を行うことができる日とし、当該受診日を診療緑に記載する)について
予約を行った上で当該患者の紹介を行った場合に算定。
------------------------------------------------------------------
上記で述べた算定とは別に、歯科・医科との連携で必要な算定「診療情報等連携共有料」において、2024年度診療報酬改定がありました。
診療情報共有料は、診療情報提供料とは別の区分であり、医科・歯科間で相互に照会(問い合わせ)や情報提供を行う際に算定できます。
診療情報提供書(紹介状)のように治療を依頼する趣旨ではなく、照会状や経過報告書に相当する文書交換を評価したものです。
・診療情報連携共有料1(120点)
<算定要件>
歯科診療を行うにあたり、歯科から医科の保険医療機関や保険薬局に対して、慢性疾患または全身疾患の管理が必要な患者に対し、
その患者の同意を得て、検査結果もしくは服用薬などを、「文書など(電話、FAX、電子メールなどを含む)」で提供を求めた場合に算定。
保険医療機関、保険薬局ごとに患者一人につき3ヶ月に1回算定可。
※歯科からの問い合わせは上記のように文書や電話などでも行えるように緩和されましたが、回答は「文書」で受け取る必要があります。
・診療情報連携共有料2(120点)
<算定要件>
別の保険医療機関(歯科診療を行うものを除く)からの求めに応じ、患者の同意を得て、治療状況、治療計画、投薬内容などの診療情報を「文書」により提供した場合に算定。
提供する保険医療機関ごとに患者一人につき3ヶ月に1回算定可。
*診療情報連携共有料の注意点*
・診療情報提供料(Ⅰ)を算定した月から3ヶ月以内に、同一の保険医療機関に対して診療情報を提供した場合は、診療情報共有料は別に算定不可。
・診療情報連携共有料は、照会先が特別な関係の場合は算定不可。
------------------------------------------------------------------
当院も患者さまの必要に応じて歯科に対して、情報を提供・共有しております。
その際どのような算定になるのか、どのような目的で情報提供するのかを確認しながら算定をしております。
今後も算定に関する新しい情報など、アンテナを張りながら算定業務に取り組んでいきたいと思います。
最後まで読んでくださりありがとうございました。