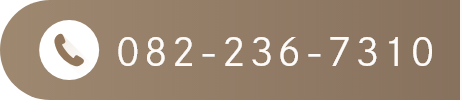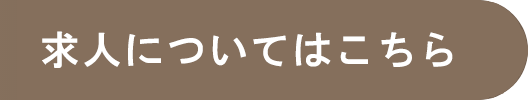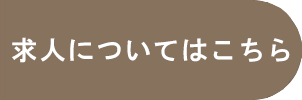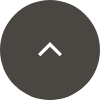訪問看護指示書の中の「手順書」について
こんにちは、算定チームです! 今回は、訪問看護指示書の中の「手順書」についてお話します。 訪問看護指示書とは、主治医が診療に基づき訪問看護の必要性を認めた際に、 訪問看護ステーションに交付する文書のことをいいます。 訪問看護指示書を交付すると、”訪問看護指示料”が月1回(300点)が算定できます。 詳しくは過去にブログで訪問看護指示書のついて掲載しているのでそちらをご覧いただければと思います。 ※ https://hinode-clinic.com/blog/186615 (2023/7/6掲載) 今回お話する「手順書」は、交付すると”手順書加算”が6ヶ月に1回(150点)算定できるのですが、 これは2022年度診療報酬改定で新たに追加された加算です。 主治医が特定行為に係る専門の管理の必要性を認め、手順書を交付した場合の報酬であり、訪問看護指示料の加算です。 ◆“手順書”とは? 医師が看護師に特定行為を行わせるために、その指示として作成する文書のことをいいます。 この手順書がないと、特定行為を行うことができません。 具体的に手順書の記載事項は以下があります。 1)看護師に診療の補助を行わせる患者の病状の範囲 2)診療の補助の内容 3)当該手順書に係る特定行為の対象となる患者 4)特定行為を行うときに確認すべき事項 5)医療の安全を確保するために医師又は歯科医師との連絡が必要となった場合の連絡体制 6)特定行為を行った後の医師又は歯科医師に対する報告の方法 ◆”特定行為”とは? 診療の補助であり、看護師が手順書により行う場合には、実践的な理解力、思考力及び判断力並びに 高度かつ専門的な知識及び技能が特に必要とされる38の行為をいいます。 当院のような在宅医療を主にやっているクリニックの患者さんは、訪問看護が介入していることが多いです。 38の特定行為のうち、訪問看護で専門の管理を必要とするものは以下があります。 ・気管カニューレの交換 ・胃瘻カテーテルもしくは腸瘻カテーテルまたは胃瘻ボタンの交換 ・膀胱瘻カテーテルの交換 ・褥瘡または慢性創傷の治療における血流のない壊死組織の除去 ・創傷に対する陰圧閉鎖療法 ・持続点滴中の高カロリー輸液の投与量の調整 ・脱水症状に対する輸液による補正 上記の特定行為は、看護師であれば誰でもできるわけではなく、 『(※)特定行為に係る看護師の研修制度』に基づいた研修である、特定行為研修を修了した看護師が 特定行為を行うことができます。 (※)特定行為に係る看護師の研修制度: 高齢者人口がピークとなり、生産年齢人口も減少し続ける2040年を見据え、在宅医療等を支える看護師を養成するもの。 ◆”特定行為研修”とは? 看護師が手順書により特定行為を行う場合に、特に必要とされる実践的な理解力、思考力及び判断力並びに 高度かつ専門的な知識及び技能の向上を図るための研修です。 特定行為研修について詳しいことは厚生労働省HPに記載がありますので、そちらをご覧ください。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077114.html (厚生労働省) 日々の算定業務において”手順書”のように様々な書類を目にすることがあるのですが、書類に対する算定項目の他に、 「なぜその書類が必要なのか」や書類に記載されている単語の意味などを調べてみるととても勉強になります。 ”ただ算定をする”のではなく、その算定に関する事柄も一緒に知っていく、ということを心掛けながら、 これからも日々算定業務に取り組んで参りたいと思います。 最後まで読んでくださりありがとうございました。
ひのでクリニック